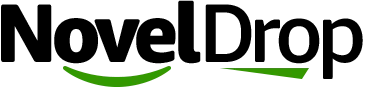京に残した忘れ物 京のいたずらっ子、世界を駆ける 教育協力専門家・半生記
著者が生まれ育ったのは、京都の下町ともいうべき下京区の松原通商店街。家業は小さな電機店。四条河原町などの有名繁華街からはちょっと離れた、四条大宮にほど近いその小さな商店街には、ご近所さんが肩を寄せ合って暮らす、濃密な人と人との繫がりがありました。著者が小学生となったのは昭和21(1946)年。だから著者の子ども時代は、戦後の復興と軌を一にします。そうしたみんなが貧しかった戦後すぐの世相を背景に、商店街あげての歳末大売り出し、大晦日の八坂神社への「をけら参り」、身近な行事だった「壬生狂言」、嵐山への「十三参り」、鴨川や蹴上の疎水での水泳、京の町を駆け抜けた学級対抗駅伝など、生き生きとした思い出が豊富に綴られます。それらは、京都人でなければ経験できない、いかにも京都を感じさせる思い出の数々です。幼い頃に父を亡くしたため母や兄を中心に家族が団結し、著者は「いたずらっ子」「立たされ坊主」として、やんちゃな子ども時代を過ごしたのですが、経済的理由から大学進学を諦めて高校卒業後に就職。そこで厚い世間の壁にぶち当たり、「この先どう生きるか」に苦悶します。そんなとき著者を鼓舞してくれたのは、そうした子ども時代の豊かな思い出でした。著者は仕事のかたわら夜間大学に通い、工業高校の教諭となり、やがて国際的な科学教育協力の先駆者としての道を切り拓きます。いつも「京に残した忘れ物」への追憶を胸に。本書は、80歳越えた今も現役の教育専門家として世界から招聘される、不屈の著者の生命力あふれる半生記です。