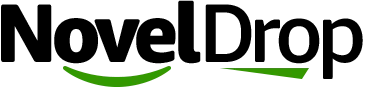菅家後集の研究
解 説
一、菅原道真について
ア、菅原道真の時代
イ、菅原道真の生涯1(大宰府左遷以前)
ウ、菅原道真の生涯2(大宰府左遷及びその後)
エ、菅原道真の宇多天皇に対する思い
オ、菅原道真の憂憤ー役人の不正を糾弾ー
二、『菅家文草』『菅家後集』について
三、菅原道真の詩の特徴
-『菅家後集』を読解するにあたってー
ア、菅原道真の詩に強く影響を与えた『白氏文集』
イ、応製詩と詩に対する考え方
四、『菅家後集』の詩を読解することの難しさ
ア、菅原道真の漢詩を読解するにあたって
イ、四七八「不レ出レ門〈七言〉」
ウ、四八二「九月十日」
エ、五一四「謫居の春雪」
菅家後集 注解
凡例
〈前田育徳会尊経閣文庫所蔵丁本(菅家後集貞享刊本首部)〉
※四六九 見三右丞相献二家集一 〔御製〕
…(中略)…
四七四 感二吏部王弾一 レ琴、応レ製〈一絶〉
四七五 冬日感二庭前紅葉一、示二秀才淳茂一
(昌泰四年)
※四七六 〔明石駅亭口詩〕
〈以下、前田家尊経閣文庫所蔵甲本〉
四七六 〈五言〉自詠
四七七 詠二楽天北窓三友詩一〈七言〉
…(中略)…
四九二 元年立春〈十二月十九日〉
四九三 南館夜聞二都府礼仏懺悔一
(延喜二年)
四九四 歳日感懐
四九五 梅花
…(中略)…
五一四 謫居春雪
奥書
後人擬作
一 御詫宣詩
二 示二勅使被一 レ返二左大臣宣命一
三 被レ贈二大政大臣一之後、詫宣
〈以下、菅家後集貞享刊本尾部。尊経閣本後集丁本尾部亦同〉
奏状
六七四 献二家集一状
六七五 重請レ罷二右近衛大将一状
おわりに
一、菅原道真について
ア、菅原道真の時代
イ、菅原道真の生涯1(大宰府左遷以前)
ウ、菅原道真の生涯2(大宰府左遷及びその後)
エ、菅原道真の宇多天皇に対する思い
オ、菅原道真の憂憤ー役人の不正を糾弾ー
二、『菅家文草』『菅家後集』について
三、菅原道真の詩の特徴
-『菅家後集』を読解するにあたってー
ア、菅原道真の詩に強く影響を与えた『白氏文集』
イ、応製詩と詩に対する考え方
四、『菅家後集』の詩を読解することの難しさ
ア、菅原道真の漢詩を読解するにあたって
イ、四七八「不レ出レ門〈七言〉」
ウ、四八二「九月十日」
エ、五一四「謫居の春雪」
菅家後集 注解
凡例
〈前田育徳会尊経閣文庫所蔵丁本(菅家後集貞享刊本首部)〉
※四六九 見三右丞相献二家集一 〔御製〕
…(中略)…
四七四 感二吏部王弾一 レ琴、応レ製〈一絶〉
四七五 冬日感二庭前紅葉一、示二秀才淳茂一
(昌泰四年)
※四七六 〔明石駅亭口詩〕
〈以下、前田家尊経閣文庫所蔵甲本〉
四七六 〈五言〉自詠
四七七 詠二楽天北窓三友詩一〈七言〉
…(中略)…
四九二 元年立春〈十二月十九日〉
四九三 南館夜聞二都府礼仏懺悔一
(延喜二年)
四九四 歳日感懐
四九五 梅花
…(中略)…
五一四 謫居春雪
奥書
後人擬作
一 御詫宣詩
二 示二勅使被一 レ返二左大臣宣命一
三 被レ贈二大政大臣一之後、詫宣
〈以下、菅家後集貞享刊本尾部。尊経閣本後集丁本尾部亦同〉
奏状
六七四 献二家集一状
六七五 重請レ罷二右近衛大将一状
おわりに