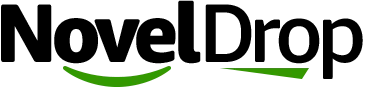恭仁京と万葉歌
本書は、恭仁京時代の万葉歌に正面から取り組んだ初めての学術書である。天平十七年(七四五)の平城還都後、万葉歌は大伴家持を中心とした私家集の色彩が強まってゆくため、恭仁京時代は家持にそれほどまでに偏らない表現研究を構想できる最後の期間でもある。
「はじめに」では、今述べた点を含めて、本書の立場が明瞭になり、本書が目指す韻文史構想が記される。
第一章「基礎的考察」は、歴史学から見た恭仁京の把握から始まり、恭仁京時代の家持の立ち位置が確認される。従来、恭仁京時代の家持を政治的な側面から捉えようとする論調が多かったが、歴史学の成果に依拠しつつ、家持を、九十人から成る聖武天皇の内舎人のひとりとして、また、大伴家の若き一員として考えるべきと述べる。その他、第二章以降の前提となるべき、本文校訂、改訓、「屋根」の意味などによって構成されている。
第二章「恭仁京讃歌」では、境部老麻呂作歌、田辺福麻呂歌集所出歌、大伴家持作の三作品の作品論が展開する。表現の質の問題から詠作時の推定まで、恭仁京時代の雑歌論となっている。
第三章「相聞往来」では、恭仁京と平城京とを行き来する相聞歌に焦点を当てる。恭仁京時代の相聞歌は家持関係歌がほとんどを占めるため、家持が、平城京に残っている女性とどのようなやりとりをしたかが活写される。結果的に、そこには実際の歌のやりとりを通じて、家持の大嬢への愛情が浮かび上がる。類型性に埋没する相聞歌に新しい光を当てる論である。また、弟である書持や、紀女郎との贈答は、第一章で述べられた本文校訂や改訓などを基に相聞の質を読みなおす。本章は恭仁京時代の相聞歌論である。
第四章「廃都へ」では、恭仁京時代の後半から平城遷都後の歌が論じられる。若き家持の大作である「安積皇子挽歌」に多くの紙数を割き、人麻呂の殯宮挽歌の受容とばかりいわれてきた当該歌を、違う角度から解き明かす。また、「独り奈良の故宅に居りて作る歌」については家持の孤独が強調されていたが、そうした先入観を捨てて、恭仁京を捨てることになってしまい、今後の定住地さえはっきりしない不安の中で作られた作であると説く。そして、「甕原荒墟歌」については、人麻呂の「近江荒都歌」の影響下にある点が強調されて来たが、「荒都歌」と「荒墟歌」との違いを明確にし、宮ではなく都の衰亡を歌っていることを論じた。本章は恭仁京時代の挽歌論といってもよい。
最後に「むすび」では、本書で述べてきた各論を通した文学史的な見取り図が示される。
本書は、単独論文に換算すると十四本の各論から成り、うち、九本が書き下ろしという、比較的珍しい形態を取るが、その分、求心的な構成になっている。たび重なる遷都がもたらした万葉歌の諸相が明らかになった。
後日入力予定。
「はじめに」では、今述べた点を含めて、本書の立場が明瞭になり、本書が目指す韻文史構想が記される。
第一章「基礎的考察」は、歴史学から見た恭仁京の把握から始まり、恭仁京時代の家持の立ち位置が確認される。従来、恭仁京時代の家持を政治的な側面から捉えようとする論調が多かったが、歴史学の成果に依拠しつつ、家持を、九十人から成る聖武天皇の内舎人のひとりとして、また、大伴家の若き一員として考えるべきと述べる。その他、第二章以降の前提となるべき、本文校訂、改訓、「屋根」の意味などによって構成されている。
第二章「恭仁京讃歌」では、境部老麻呂作歌、田辺福麻呂歌集所出歌、大伴家持作の三作品の作品論が展開する。表現の質の問題から詠作時の推定まで、恭仁京時代の雑歌論となっている。
第三章「相聞往来」では、恭仁京と平城京とを行き来する相聞歌に焦点を当てる。恭仁京時代の相聞歌は家持関係歌がほとんどを占めるため、家持が、平城京に残っている女性とどのようなやりとりをしたかが活写される。結果的に、そこには実際の歌のやりとりを通じて、家持の大嬢への愛情が浮かび上がる。類型性に埋没する相聞歌に新しい光を当てる論である。また、弟である書持や、紀女郎との贈答は、第一章で述べられた本文校訂や改訓などを基に相聞の質を読みなおす。本章は恭仁京時代の相聞歌論である。
第四章「廃都へ」では、恭仁京時代の後半から平城遷都後の歌が論じられる。若き家持の大作である「安積皇子挽歌」に多くの紙数を割き、人麻呂の殯宮挽歌の受容とばかりいわれてきた当該歌を、違う角度から解き明かす。また、「独り奈良の故宅に居りて作る歌」については家持の孤独が強調されていたが、そうした先入観を捨てて、恭仁京を捨てることになってしまい、今後の定住地さえはっきりしない不安の中で作られた作であると説く。そして、「甕原荒墟歌」については、人麻呂の「近江荒都歌」の影響下にある点が強調されて来たが、「荒都歌」と「荒墟歌」との違いを明確にし、宮ではなく都の衰亡を歌っていることを論じた。本章は恭仁京時代の挽歌論といってもよい。
最後に「むすび」では、本書で述べてきた各論を通した文学史的な見取り図が示される。
本書は、単独論文に換算すると十四本の各論から成り、うち、九本が書き下ろしという、比較的珍しい形態を取るが、その分、求心的な構成になっている。たび重なる遷都がもたらした万葉歌の諸相が明らかになった。
後日入力予定。